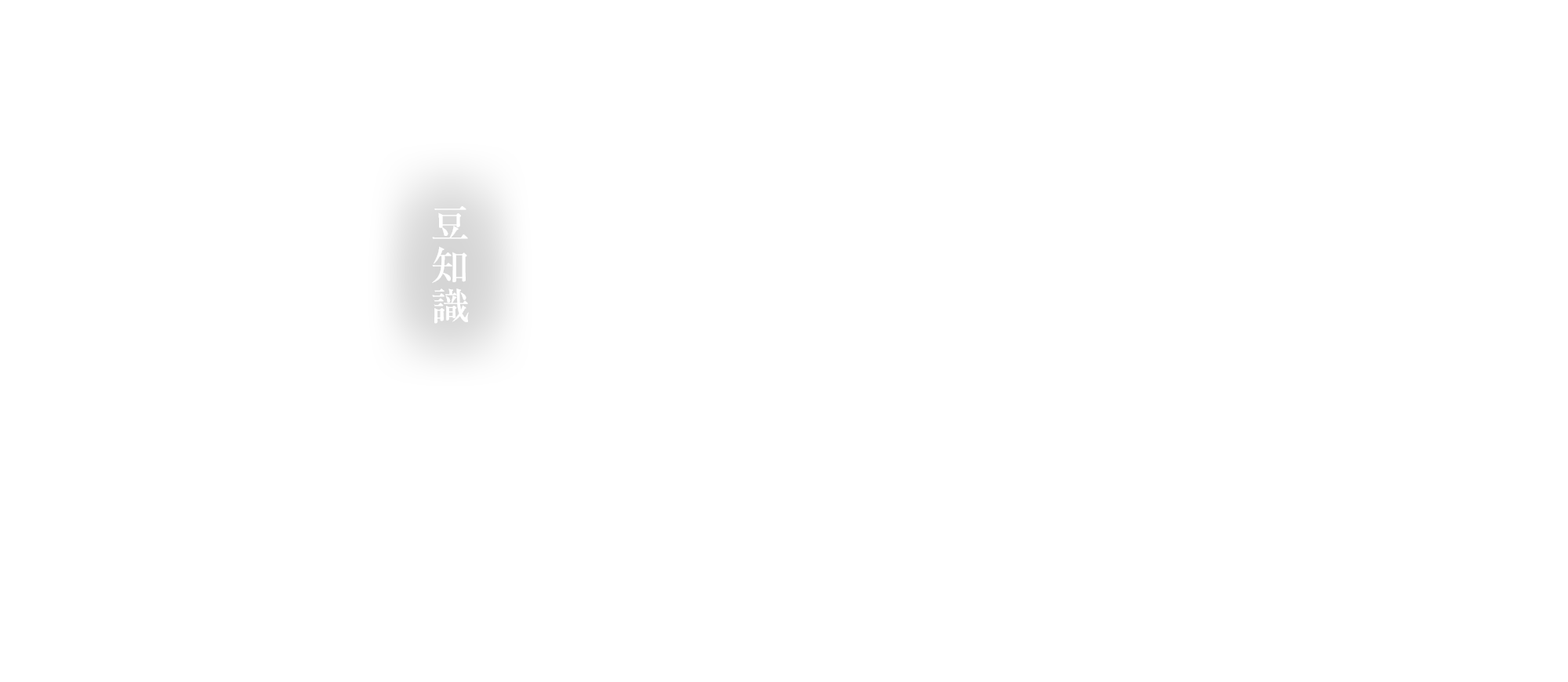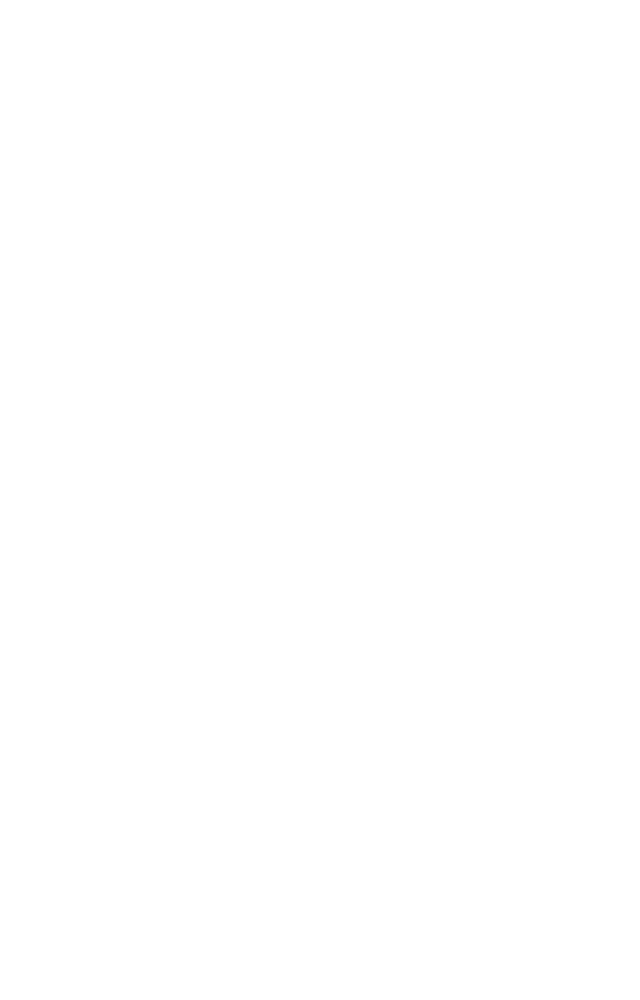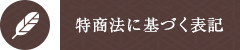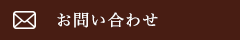美味しいおだしのとりかたです。
おだしの取り方【お吸い物】①
吸物の場合、利尻昆布は、本鰹の約半分の重さで、吸物だと一人分(水200cc)に対して昆布5g(ハガキ半分程度の大きさ)に本鰹を10gが基本です。
ここでは水2リットル、昆布50g、本鰹100gを用意します。
おだしの取り方【お吸い物】②
利尻昆布の表面を布巾でさっとふき、水に入れ火にかけます。昆布の入った水が沸騰直前(鍋の底からポツポツと泡が出てくるころ)に昆布を取り出し、コップ 一杯程度のさし水をして、昆布だしの温度を下げます。
そこへ本鰹100gを入れて鰹が沈むのを待って(30秒ぐらい)火を止めて布巾かキッチンペーパーを敷いた濾しざるで濾しますが、絞らないでください。
少量の塩と醤油で味をととのえれば、吸物のだしが出来上がります。

おだしの取り方【味噌汁・煮炊きもの】
味噌汁、煮炊き用のだしは、水2リットルに対して、昆布30g~50g、だしかつお(ここでは、おもに鯖、うるめ、いわしなど)100gを使います。
水に昆布を入れて火にかけ、沸騰してきたら、昆布を引き上げて出しかつおを入れます。アクをとりながら弱火で3分くらい煮だし火を消して布巾かキッチン ペーパーを敷いたざるで濾します。
だしがらは絞ってエキス分を十分出していただいても結構です。
昆布はワインと似ている?
昆布は主に東北地方と北海道で生産されており、海流の違いによって種類や特徴が異なります。ワインと同様に、産地(浜)、規格、格付けによる区分がしっかりとされています。主な昆布の種類には、真昆布(松前昆布や山だし昆布など)、利尻昆布、鬼昆布(羅臼昆布)、三石昆布(日高昆布)、長昆布、細目昆布があります。近年では、ガゴメ昆布のネバリ成分による健康効果が注目されていますが、本来の昆布でも十分に健康に良いので、ぜひ日常的に昆布を使うことをオススメします。

ダシ昆布の選び方
昆布を選ぶ際、産地や浜の違いと同様に、天然か養殖かという点も非常に重要なポイントです。養殖昆布は安定供給が可能ですが、天然もののまろやかな味わいと上品な甘み、深いコクには到底かないません。一般的に、広く真っ黒な昆布が良いとされていますが、実際には違います。天然昆布は、採れた浜にもよりますが、厚みがあり、幅が狭くシワシワで見た目はあまり良くないものの、品質が優れ、美味しいものです。光に透かすと濃い飴色になるのも特徴です。

ダシ昆布の使い分け
当店で取り扱っているダシ昆布は、松前、利尻、羅臼の3種類です。それぞれに特徴があり、使いやすさや味の好みに合わせて選んでいただくのが一番です。例えば、気軽に使えて煮立たせても問題ない松前昆布は、普段使いに最適です。少し高級感を求めて昆布の香りを引き立てたい料理には利尻昆布がぴったり。さらに、昆布独特の旨味や風味を強調したい料理には、羅臼昆布を使うと、味わいが深まります。用途に応じて使い分けてみてください。

ダシをとるときの注意点
昆布の水温を70℃以上に上げると、鰹のタンパク質が凝固し、白く濁ったダシが出ます。これは、ダシに含まれるタンパク質が加熱されることによって起こる現象です。また、稀に水道水のカルキや昆布に含まれるヨード、鍋に残った澱粉が反応し、ダシが青色に変色することがあります。この現象は「ヨードデンプン反応」と呼ばれ、ダシの色が変わることがありますが、味には大きな影響はありません。

昆布の種類と特徴をご紹介
当店で取り扱っている昆布の種類と特徴をご紹介します。
使い方については、初めて使う方へのオススメ程度です。
色々とお試し頂いて、お好みの味や使い方を見つけて頂くのが一番と考えております。